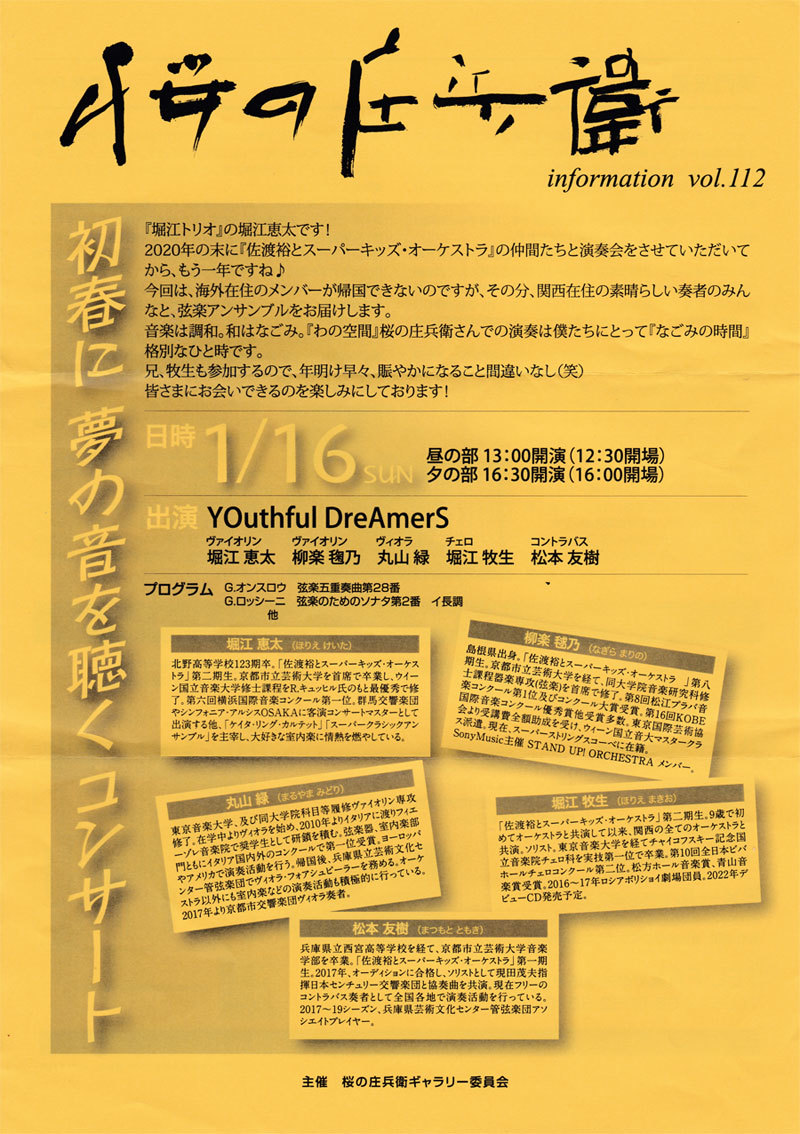たとえ世界が明日滅びるとしても、私は今日、リンゴの木を植える。

水や空気や土や種が、地球そのものが特定の誰かのものになる
1月22日、難波希美子さんの呼びかけで、「タネを考えよう」の集まりを能勢町淨瑠璃シアター研修室で開催しました。
コロナ感染症オミクロン株が広がる中、開催をどうしようかと思い悩みましたが、わたしたちなりに感染対策を万全にしながらの集まりでした。
たとえ世界が明日滅びるとしても、私は今日、リンゴの木を植える。
この有名なマルチン・ルターの名言は、「世界がどんなに絶望の淵にあっても、かならずやってくる未来の世代に希望を託し、あきらめないで今日できることをしよう」という意味と思ってきました。そこには、人の世はよくも悪くも変わっていくけれど、森や山や川や海がいつまでも変わらずわたしたちを見守ってくれているという思いが込められています。
しかしながら、利益を増やし成長するために倒れるまで走り続けなければならない人の世の資本主義の宿命は、わたしたちを見守ってくれていたものまで商品に変えてしまいました。水や空気までもが商品になり、地球そのものから宇宙までも私有化の終着駅へと驀進する今、人間が途方もない時を地球と共に耕し、分け与えられてきた恵みとしての種や苗もまた、長い歴史の末に「誰のものでもなくみんなのもの」から「特定の誰か」のものになってしまおうとしています。
2018年、主要農作物種子法が廃止されました。種子法とは1952年、戦後の食糧難の折、コメや大豆、麦などの普及を促進するため、命の要である主要食料のその源である種は民間に任せるのでなく国が責任を持ち、国がお金を出して都道府県がいい種を開発し農家に安く提供する法律でした。
種子法廃止により種子を公的に守る政策が放棄されたことにより、一部企業による種子開発や品種の独占など、多国籍企業に日本の食料を支配されることにつながります。
そこで農業が主要産業である地方自治体では、種子法が廃止された後も独自のシステムで原種の保管などこれまでの取り組みを継続するために、種子法と同様の趣旨の内容を盛り込んだ種子条例を制定しており、2021年4月現在、北海道と27県に達しています。
さらに昨年の国会で種苗法の改定が決まりました。種苗法とは、野菜やくだもの、穀物、きのこや花などのすべての農作物の種や苗に関する法律で、新たに開発された品種を農水省に出願して、それが認められて「登録品種」となると、その独占的販売権が25年(樹木の場合は30年)認められます。これまでは農家は自分の作った作物から次の作付けのために自家採種してもよかったのですが、今回の改定で育成者に許諾を得なければ自家採種ができなくなります。
主に日本の種を海外に取られないための改定とされていますが、種苗法で自家採種に制限をかけるだけでは海外流出の歯止めには不十分だと言われています。むしろ、「種は買う」ものとなって、日本の農家がグローバル種子企業に譲渡されたコメなどの種を買わざるを得ない状況になり、表面上の意図とは逆に日本の種を海外企業に取られ、支配されてしまいかねません。
各地域の在来種は地域農家と地域全体にとって地域の食文化とも結びついた一種の共有資源であり、個々の所有権は馴染まないのではないかと思います。企業がそれを勝手に素材にして品種改良して商品化を進め、その種を買わなければ作物を作れないとすると、それでなくても高齢化と後継者不足に悩み、先行きに自立した経営が困難な小規模農業や家族農業に追い打ちをかけることになります。
誰かのものからみんなのものに、種には先人たちの愛おしい記憶がつまっている
わたしは能勢町に移住して10年半になります。それまでは妻の母親と吹田市の緑地公園駅の近くに住んでいたのですが、都会暮らしより地元の米や野菜をふんだんに味わえるところで暮らしたいと妻が提案し、妻の母親と3人で能勢に移住してきました。
当初は近所にある道の駅で買っていたのですが、その内に農家の人たちと知り合いになり、また若い頃に知り合った能勢農場や産直センターとの付き合いも再開し、地元の農家などから直接野菜を買うことも多くなりました。そして、農業の大変さ知り、消費者の目線だけで値段を気にしたり安全な農作物を買うことに疑問を持つようになりました。地元農家に分けてもらう野菜はほんとうに安くて新鮮で、年金生活のわたしたち夫婦にはとてもありがたいのですがその一方で、そのことが農家の生計が成り立たない厳しい現実とかなしく釣り合っていることを痛いほど感じます。
地産地消という形で地域の間で生活経済が回っていくためにも、また食料自給率の極端の低さからみても、さらには里山に囲まれた小さな土地を有効に利用するためにも、わたしは土地を集約し、流通コストをかけて成長する大規模農業への道より、長年の政策によって追い詰められ、苦しめられる小規模農業が持続可能になるための経済的支援、人的支援が求められていると思います。そしておそらく、無農薬栽培など有機農法や自然農法は、生産者のすぐそばにいる子どもたちの顔が見える小規模農業によってしか広がっていかないのだと思います。
種子を公的に守ってきた種子法の廃止や、自家採種を制限する種苗法の改定は、遠い昔は「みんなのもの」であっただろう種子をかぎりなく私有物にする道なのでしょう。少し大げさに言えば最初は土地の収奪から始まり、工業化によるイノベーションの道を時速300キロで走ってきた末に、最後のフロンティアとしてわたしたち人間の身体と心を対象にし、商品化する一方、環境ビジネスの対象として地球そのものをターゲットにしようとする市場経済的野望のひとつの現れなのだと思います。
今わたしたちの手元にある種たちの中には、自生を繰り返してきた種も、また人間と自然が時には争いながらも共に育ててきた種も、何年、何十年、何百年、そしていくつもの世紀を渡り、人類誕生から始まる途方もなく長い時をくぐりぬけ、次の世代へと命と希望と切ない夢をつないできた先人たちの愛おしい記憶がいっぱい詰まっているのだと思います。