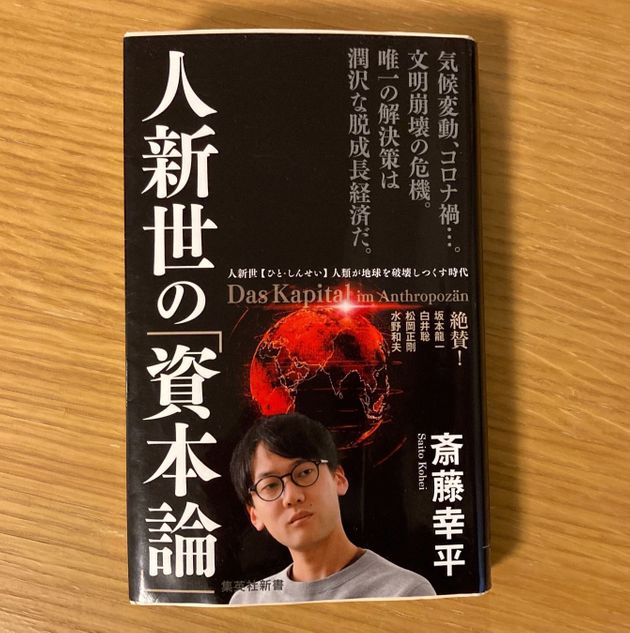井上陽水の「傘がない」とわたしの青春

1972年2月19日、長野県軽井沢町の保養所「浅間山荘」に、「連合赤軍」のメンバー5人が逃げ込み、山荘で留守番をしていた管理人の妻を人質に立てこもりました。事件発生から10日目、警察は人質救出のため「突入」を決断。作戦開始から8時間超…人質救出に成功、犯人全員が逮捕されました。その模様はテレビ中継され、最高視聴率は90%に達し、国民のほとんどがテレビを見ているという空前の出来事でした。
その時、わたしは工場勤めにもようやく慣れ、5時に仕事が終わるといつものように同僚たちと卓球をして遊んでいました。その部屋にはテレビがあり、事件の一部始終を映していました。
工場の年配の女性たちに、「あんたらも同じとちゃうか」と言われ、ぎこちなく「ぼくらはちがうで」と言い訳けするわたし自身に腹立たしく、言葉にできない寂しさや悲しさに襲われました。もちろん、わたしは彼女彼らとはちがうどころか、学生運動や70年安保闘争ともまったくかかわりがなかったにもかかわらず、なぜか同じ世代の人間として、彼女彼らと一緒に何か大きなものをなくしたような気がしたのです。
寺山修司が「犯罪は失敗した革命である」と言い、「彼らをさばけるのは、コーヒーなどを飲みながらテレビを見ているわたしたちの国家ではなく、彼らが夢見た国家の中でしかないだろう」と言った言葉を覚えています。
1969年の正月、わたしは22才になっていました。部屋の中はまだ暖房の残りで暖かそうでした。その部屋はともだちの部屋で、その日数少ない友だちが5、6人、わたしを待っていてくれるはずでした。
このときわたしは風邪をこじらせ、吹田駅前裏のアパートに帰るところを咳がひどく、熱もいっこうに下がらない状態で、摂津市千里丘の実家でずっと寝ていたのでした。わたしは高校の頃からこの家を早く出たいと思っていました。36才でわたしを生んだ母も、たったふたりきりの兄弟の兄もけっしてきらいではなかったし、むしろ子どもの頃から世間になじまないわたしをとても心配してくれていました。でもわたしは、とにかくこの家から離れたかったのでした。
父親がどんなひとなのかもわからない愛人の子…。そのことでわたしたち子どもがひけめを感じないように父親と別れ、養育費ももらわず朝から深夜まで一膳飯屋をしてわたしたちを育ててくれた母。その頃は店をたたみ、近所の工場の給食係として働き、自分が早くに死んだ時に息子たちが困らないようにと切ない貯金をしていた母。どれだけ感謝してもしきれない、いとおしい母のはずなのに、わたしはそのことすべてからさよならをしたかったのでした。わたしは不憫な子でも、母が苦労してよかった思える親孝行の息子でもありませんでした。
わたしは高校卒業を待ってすぐ、家を出ました。
どれだけ待ったことでしょう。ともだちはいっこうに帰って来ませんでした。この日はとくに寒く、まして悪い咳が止まらず熱もあるわたしには、その寒さに耐える時間がそう長くあるわけではありません。
「血のつながった親兄弟と、あかの他人のともだちとどっちが大事やねん。どっちがお前を大切にしてるねん」。約束だからと起きるわたしを羽交い絞めにおさえて叫んだ母と兄。
「ともだちや」と叫び、「勝手にせえ、お前なんかもう知るか」と言った兄の声を背中に受けて家を飛び出してきたわたしは、もちろん実家に戻ることもできず、長い間留守にしていた吹田のアパートに帰りました。
結局わたしはそれから一週間以上も寝込んでしまいました。実家にも知らせず、ともだちとも連絡をとりませんでした。テレビもなく、わたしをかろうじて社会につなぎとめていたラジオからは1月18日、東大構内の安田講堂に立てこもった全学共闘会議派の学生を排除しようと、機動隊によるバリケードの撤去が開始されたことを伝えていました。
高度成長、ベトナム戦争、安保闘争、東京オリンピック、アメリカ公民権運動など、世界も日本も激動の時代だった1960年代を、ぼくは同世代の学生運動にシンパシーをもちながらも、パッとしない青春を悶々と過ごしていました。
政治の季節といわれたその時に、わたしはと言えば高校の紹介で就職した会社を半年でやめ、ビルの清掃をしながら夜になると大阪の繁華街の片隅の「いかがわしい」お店に入りびたっていました。そこには薬とけんかとダンスと酒とたばこで退廃的な夜を費やす、学生運動の若者とはまったくちがう若者たちがいました。ある日、店員が「おまわりだ」と叫び、みんな一斉に逃げ出し、わたしも逃げました。あくる日、店に行くと、その店はもう閉店の張り紙があるだけでした。
今でも思うのです。あの時たくさんいた若者たちはどこに行ったのでしょう。そして、路上で石を投げ、ゲバ棒を振り上げ、機動隊に痛めつけられた若者たちも、みんなどこに行ってしまったのでしょう。1970年、わたしもまたよど号事件とビートルズの解散とともに、神戸の須磨の砂浜に意味もなく大きな石を放り投げ、わたし自身の青春とお別れしたのでした。
ついさっきまで吹き荒れた激動の嵐が一瞬にして納まり、何事もなかったように世の中が高度経済成長へとアクセルを踏み、バスに乗り遅れるなと誰もがその新しい風に巻き込まれていく時、何者にもなれなかったわたしもまた、納得できない現実と行方不明になった夢とのはざまでもがき、時代に取り残された寂寥感に包まれました。
「傘がない」は、そんなわたしの心情にぴったりの歌でした。一般的に社会や政治の問題よりも、恋人に会いに行くのに傘がないことが問題だと歌うこの歌は、あれだけ若者の叛乱におびえていた大人たちを内心ほっとさせ、政治に関心がない自分本位の若者を批判するためのかっこうの歌と思われました。
しかしながら、同じ世代の若者のひとりとして、絶望感と隣り合わせの新しく開かれた時代の扉の前に立ち、ボブ・ディランの歌がそうであるように、政治や社会の既成のタブローに収まらなくなった新しい時代をたぐりよせたのだと思います。時として恋歌が政治のはらわたをえぐり、社会の薄明るい未来を透かしてみせてくれることがある、初めての歌だったのかもしれません。
そのことを敏感に感じ取ったジャーナリストが筑紫哲也さんでした。ずっと後に被災障害者支援「ゆめ風基金」のトークイベントでお世話になった筑紫さんは、1974年、朝日新聞の特派員を経て帰国した頃、銀座のシャンソンバーで「傘がない」を聴き、「すごいのが出てきた」と思ったそうです。筑紫さんは後に「これは足払いの歌なんだ。天下国家をしかつめらしく言う世の風潮に対する足払いなんだ」と語っています。
そしてはキャスターを務めたテレビ朝日「日曜夕刊!こちらデスク」で「傘がない」を流しました。彼は深刻な顔で自国の将来を語るような憂国の番組にしてなるものかと思っていたのでした。陽水はその放送を観て「ちょっと生意気な言い方になりますが、ああ、この人は相当、わかってるなと思いました。ジャーナリズムに身を置きながら、ジャーナリズムを突き放して見ることができる。ある意味で、ユーモアがわかる人なんだ」と筑紫さんの死後、陽水は語っています。
それからの深い縁の中で、TBS「ニュース23」の最初のエンディングテーマ「最後のニュース」が生まれたのでした。
井上陽水の「傘がない」は、発売日は1972年ですが、つくられたのは1970年と聞きます。井上陽水もまた、政治の季節の真ん中で「何者かになろうとして何者にもなれなかった」当時のわたしをはじめとするたくさんの若者たちと共にいたのではないかと思います。
たとえば青春は
暗い路地を走り抜けた後に広がる青空
廊下に出るその一瞬に部屋に残した風
飛び乗った列車の窓から行方不明になった
もうひとりのぼく
長い時間を貯金した忘れ物の傘のように
たとえばそれがぼくの青春
長い非常階段の踊り場で
行方不明のぼくたちが手をふっている
洗いざらしのTシャツを着て
街に出て映画でも見に行こう
まばたきをするだけで世界は変わる