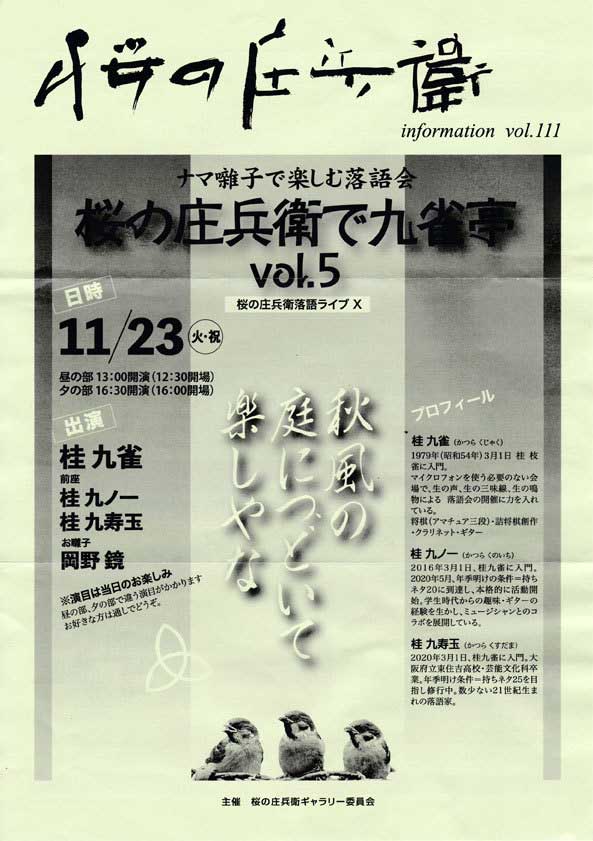松井しのぶと阪神大震災と焚き火の思い出

やがて悲しみは希望にかわり
新しい星が生まれます
生まれたての星はまだ
光ることができません
だから星は焚き火をして
光る練習をするのです
今夜もほら、あんなに赤く
星がにじんでいます
その絵は焚き火の絵だった。四人の人間が焚き火をしている。その炎からいくつもの星が生まれる。そのうちのひとつの星が大地に堕ちてなお、きらきら光る。
全体がオレンジ色の小さな絵の中で、果てしない大きな空間がわたしたちを包む。そこには無数の悲しみがかくれていて、焚き火はそのひとつひとつをいとおしくすくい上げるのだった。
2003年、急逝された吉田たろうさんに代わってカレンダーのイラストを描いてくれるひとを探していたわたしの目に飛び込んできた一枚の絵が、松井しのぶさんとの出会いだった。
焚き火の思い出
中学生の時、冬休みに一度だけアルバイトをしたことがある。僕の家には父がいなくて、母が飯屋をしながらわたしと兄を育ててくれた。今は中学生のアルバイトは禁じられているらしいが、そのころは家計を助けるために新聞配達をしたり知り合いのお店や工場でアルバイトをする友だちもいたように思う。僕の家の状況から言えば真っ先にアルバイトをしてもあたりまえだったが、母はそれを嫌っていた。店の手伝いをしてほしかったこともあるが、なによりも勉強してほしかったのだと思う。
1960年には高校進学率は67%に達してはいたらしいが、それでも貧乏な家庭の子どもは就職して家計を助けるのがふつうだった。そんな時代に自分の身体がこわれても「高校だけは行かせたい」という母の切実な願いは、いわゆる私生児でよりどころがない子どもが生きていくには学問しかないという切なくて頑固な信念から来ていた。
そんなわけでわたしは学校から帰るとお店の手伝いをしながら、空いたテーブルで勉強していた。そのおかげでわたしの教科書もノートも醤油やソースのこぼれたあとがいつもへばりついていた。
どんないきさつだったのかおぼえていないが、アルバイト先はわたしの数少ない友人で、似たような境遇だった同級生の家がやっていた工務店だった。いまから思えばわたしたち家族の生活への気づかいと対人恐怖症で引っ込み思案のわたしを心配して、その友人の母親がわたしの母を説得してアルバイトをさせてくれたのだと思う。
仕事は南大阪の大和川河川敷でのボーリング地質調査の手伝いだった。おそらく仕事にはならず、職人さんの足を引っ張って迷惑をかけたことと思う。ともあれわたしは冬休みのほんの一週間、働かせてもらった。
寒い朝、工務店に着くと数人の職人さんが大きなドラム缶に廃材を放り込み、焚き火をしていて、「冷たいやろ、早よあったまり。」といつも声をかけてくれるのだった。
身体がかちかちになっているわたしは焚き火に差し出した両手から、あたたかさを身体の中にゆっくりと流し込む。パチパチと木がはぜる音、ぼんやりとゆれる炎。顔のほてりを両手でこすりながら、わたしは心の中の何かかたくななものがとけていくのを感じていた。その15分ほどの時間がとてもうれしかった。
わたしは焚き火の楽しさを教えてもらった。今思い返すとそのあたたかさは焚き火だけのせいではなく、特別な事情をかかえる子どもを温かく見守る職人さんたちの心づかいだったのだと思う。
共に生きる勇気を育てるために
阪神大震災の時、公園や学校などの避難所ではどこでも焚き火をしていた。5500人以上のかけがえのないいのちがうばわれ、あたり一面が瓦礫の荒野となってしまったその地で凍てつく冬の夜を照らす焚き火は、体をあたためることや灯りをとることや炊き出しをするためだけに必要だったのではない。多くの証言が語るように焚き火は被災地のひとびとの心をあたため、癒してくれたのだと思う。
余震の恐怖、肉親や恋人、友人を失った無念、生き残ったがゆえにおそいかかる死の予感…。廃材といっしょに何度も何度もそれらをドラム缶の中に投げ込み、ひとびとは焚き火をしつづけたのだった。それは5500を超えるたましいを見送る儀式でもあったが、それと同時に生き残ったひとびとが助け合って生きる以外に道はないことを教えてくれる、だれもが必要とした道しるべでもあった。
阪神大震災はこの社会が安全ではないことを教えてくれたことで、直接被災しなかったひとびとにも深い傷を残している。その後次々と起こる大災害、無差別テロ、信じられない事件…。今振り返るとあの地震はその後のとてつもない悲しみと無数の死を予感していたのだと思う。そしてわたしたちの社会はまだ、「安全で平和な社会」のあり方を見つけ出せないでいる。
けれども、どんな強力な武器よりも、共に生きる勇気を育てること以外に「安全で平和な社会」をつくれないこともまた、たしかなことなのだと思う。わたしたち人間は言葉も個性も希望も夢も国籍も民族も性別も年代もちがっても、つながることができるのだ。それがとてもうれしいことなのだと、焚き火が教えてくれた。
地震から一週間後、被災障害者に救援物資を届けるためにはじめて被災地に入った。川のそばの大きな公園で焚き火を見た瞬間、子どもの頃のあの焚き火とそれをかこむやさしいまなざしを思い出した。
ひとはずっと昔から焚き火をすることで、小さな悲しみも想像を越える大きな悲しみも分かち合い、共に生きる勇気を育ててきたのかも知れない。
松井しのぶさんの焚き火の絵は、まるでずっと前からわたしを待っていたかのように「冷たいやろ、早よあったまり。」とやさしくささやいた。わたしは焚き火に両手を差し出して、「ただいま」と言った。
やがて悲しみは希望に変わり
新しい星が生まれます
(採録2004年HPより 2014年ブログ校正)