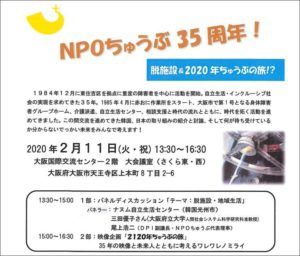島津亜矢に今もっとも必要なのは時代の風を受け止められる歌の作り手
2月12日、NHK-BS放送「歌のあとさき」の島津亜矢特別編を観ました。この番組は事前に金曜日の午後8時45分から9時の15分を4回放送したものをまとめて1時間番組として放送されました。
わたしは15分番組を見逃していたので、特別編を観ることができて幸運でした。
昨年の紅白以来、まとまった形で島津亜矢の出演番組を観ていなかったことと、ずいぶん久しぶりに彼女の歌手人生をあらためてふりかえる意味ではとてもうれしい番組でした。
しかしながら、島津亜矢の歌手人生を振り返る15分のストーリーとともに歌われた歌は、やむを得ないこととはいえ今の島津亜矢の立ち位置とはすこしちがいました。
というのも、ここ直近の島津亜矢への注目は「演歌」以外のポップスの歌唱に向けられているからです。その意味では最後に一曲だけでもポップスを歌えばよかったのかも知れません。
しかしながら、この番組はむしろ昔からの島津亜矢のファンが、ポップスのメインストリームに躍り出た彼女の活躍を喜び、共に歩んできたこれまでの苦難の道を振り返る機会を用意することに意味があったのだと思います。
選ばれたセットリストはすべてオリジナルで、「愛染かつらをもう一度」、「海鳴りの詩」、「大器晩成」、「感謝状~母ヘのメッセージ~」、「帰らんちゃよか」、「いのちのバトン」、「瞼の母」、「凛」でした。どの曲も、彼女の歌手人生の節目節目の曲で、わたしのブログでも何度も取り上げてきました。
わたしは2009年から島津亜矢のファンで、最初の頃のエピソードも歌もあとから知ることになりました。その頃でも音楽番組への露出は極端に少なくて、「島津亜矢」と言っても周りで知らない人の方が多く、わたしはもっぱらコンサートとユーチューブで彼女の歌に傾倒していきました。
最初は彼女の声量と声質、思いっきりの良さに心を奪われる一方で、音楽番組では控えめで表情も硬く、また彼女への評価もあふれる声量と歌唱力を誉める言葉の端々にもやや斜めに引きながら遠巻きに囲むような、微妙な緊張感が漂っていました。
もともと青春時代にはビートルズからはじまり、ポップスやロックに親しんでいたわたし自身も、彼女の歌には圧倒されるものの刃のような鋭い切れ味が、彼女の歌を少し頑ななものにしているように感じていました。今回の番組で彼女自身が語っているように、彼女は座り心地の悪い「演歌」の片隅の席で、心を縮ませながら必死に歌ってきたのだと思います。
「愛染かつらをもう一度」から「海鳴りの詩」まで、星野哲郎が彼女に注ぎ込んだ「愛の歌」には、演歌の巨匠のひとりと言われた星野哲郎でさえも想像できない来るべき島津亜矢の時代を夢みて、風が吹きすさぶ突堤に立ち、巨大な海から押し寄せる波を真っ白なキャンバスに必死に描こうとするある種の凄味を感じさせます。
実際、高木東六をして「えん歌の申し子」と言わしめた稀有の才能の塊だった島津亜矢を一躍スターダムに押し上げるプロデュースを阿久悠ができて星野哲郎ができないはずはなかったと思うのですが、なぜか彼はそうしなかった。
星野哲郎が彼女に託したデビュー曲「袴をはいた渡り鳥」はひいき目に見ても15歳の少女が歌うには時代錯誤ではなかったのかとわたしは思います。時代はすでに演歌では表現されないスピードで疾走していて、ロックの生々しくとがった刃も好まぬ若者たちは「Jポップ」へと心を急がしていたのですから…。
そんなことを知らないはずもない星野哲郎の執念ともいえる歌ごころは、やがて2003年の「風雪ながれ旅」で彼の思う歌の至高点にたどりついた一方で、2005年に「大器晩成」を島津亜矢に授けました。デビューから20年、決して順風満帆ではなかった彼女の歌手人生そのものを語っているようなこの歌にもまた、星野哲郎はその後もつづく彼女のいばらの道を予見し、腐らずに地道に歌いつづけることを島津亜矢に要求し、島津亜矢もまたその教えをまっとうしたのでした。
一時代をつくった稀有の作詞家がすでに自分の時代が終わっていることを認識していたからこそ、最後の愛弟子・島津亜矢の無限に近い可能性を信じ、彼自身の描く未来よりもはるかに大きな未来を島津亜矢が自ら切り開いていく力を信じた星野哲郎…。そして、いつの日か時代が島津亜矢に追いつく日が来ることを願っていた星野哲郎がこの世を去った後、島津亜矢の本当の進化が始まったのだと思うのです。
まずは座長公演という演劇体験によって、歌を歌いきるのではなく、聴く者の心に歌い残すことを学んだでしょうし、演歌を出自として、スターダストのように消えていった無数の歌たちのたましいに触れ、歌の中にあるいくつかの物語をたどり、歌の墓場からフェニックスのように歌をよみがえらせ、そのエネルギーは演歌・歌謡曲からポップス、ロック、シャンソン、リズム&ブルースにまで届くようになりました。
そして、突然やってきたブレイクは彼女を戸惑わせたものの、音楽のメインストリームに突然現れた不思議なボーカリストとしてその立ち位置を固めたのではないかと思います。
そして今、彼女は歌うのが楽しくて仕方がないのでしょう。ちょっと怖いぐらいに全身から歌があふれ出るようです。以前にも書きましたが、ポップスを歌うだけでなく、さまざまなジャンルの違いを超えたコラボレーションが、長い間眠っていた歌の女神を目覚めさせたようなのです。そこではメインボーカルよりもコーラス、バンドに例えればベースのように、音楽を支えつくる才能が発揮されるようなのです。
そこで目覚め、育てられ、耕された音楽的冒険は演歌の歌唱に最大限に生かされ、不必要なうなりやコブシがそぎ落とされることで古い演歌に新しい血が流れ始め、いよいよ「島津演歌」の始まりを暗示しているようです。
とはいえ、わたしはかねてより1970年代の「演歌」ではなく戦前戦後脈々と連なる歌謡曲にまですそ野を戻した島津亜矢の新しい歌を望んでやまないのですが、果たして時代が彼女に追いつこうとする今、ポップスのジャンルも含めた歌の作り手と共に「時代の風」を受け止め、島津亜矢の可能性をどれだけ信じ、広げられるかが彼女のチームに課せられた喫緊の課題ではないかと思います。願わくば、今はまだ有効な「歌怪獣」という称号が色あせてしまわない間に…。
瞼の母「島津亜矢」
この歌唱は若い時の歌唱で、今の歌唱は、わたしの我田引水ですがサルトルの実存劇のようで、メリハリの効いた今の歌唱の方がわたしは好きです。
わたしは子どもの頃に母がしていた大衆食堂に街の映画館のポスターを張っていた見返りでもらった鑑賞券で東映の時代劇を見ていて、錦之助の「瞼の母」を観ました。わたしは島津亜矢の「瞼の母」は大衆演劇の定番の歌ではなく、錦之助の伝説的ともいえる鬼気迫る忠太郎そのままに、「母もの」の時代劇として、堅気には戻れない宿命を背負った渡世人・忠太郎が「テロリズム」と「母を乞う子ども」との間で引き裂かれる心の痛みを表現していて、わたしの大好きな歌です。