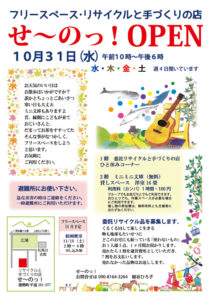若松孝二もまた映画で革命を夢見たひと 映画「止められるか、俺たちを」

少し前になりましたが、10月24日、十三の第七芸術劇場で、映画「止められるか、俺たちを」を観ました。
井上淳一脚本・白石和彌監督作品「止められるか、俺たちを」は、2012年に逝去した若松孝二監督が代表を務めていた若松プロダクションが、若松監督の死から6年ぶりに再始動して製作した映画です。
1969年から71年を時代背景に、若松プロダクションの門を叩き、助監督として奔走した吉積めぐみの目を通して、若松孝二ら映画人たちの生き様を描き、激動の時代の一瞬のきらめきを現代に定着させたこの映画は、若松孝二と若松プロに縁の深い役者とスタッフたちの若松孝二への熱い思いと、映画への情熱にあふれた青春映画です。
1969年春。21歳の吉積めぐみ(門脇麦)は、新宿のフーテン仲間のオバケ(タモト清嵐)に誘われ、若松プロダクションの扉を叩く。当時、若者たちを熱狂させるピンク映画を作り出していた若松プロダクションは、監督の若松孝二(井浦新)を中心とした新進気鋭の異才たちの巣窟であった。
小難しい理屈を並べ立てる映画監督の足立正生(山本浩司)、冗談ばかり言いながらも全てをそつなくこなす助監督のガイラ(毎熊克哉)、飄々とした助監督で脚本家の沖島勲(岡部尚)、カメラマン志望の高間賢治(伊島空)、インテリ評論家気取りの助監督・荒井晴彦(藤原季節)など映画に魅せられた何者かの卵たちが次々と集まってきた。撮影がある時もない時も事務所に集い、タバコを吸い、酒を飲み、ネタを探し、レコードを万引きし、街で女優をスカウトする。そして撮影がはじまれば、助監督は現場で走り、怒鳴られ、時には役者もやる。その中で、めぐみは若松孝二という存在、なによりも映画作りそのものに魅了されていくのだった …。
わたしの青春と重なる1969年の時代のにおいは、この映画の登場人物の誰彼となく吸い続けるたばこの煙そのものだったのかもしれません。何者かになれると信じて何者にもなれない自分にいら立ち、もがいた青い季節に、わたしは「世の中を変える」若者にはなれなくて、「世の中から永遠に逃走し続ける」ことを夢想していました。
あの時代、今日よりも明日がよくなるという幸福幻想に惑わされ、押しつぶされそうになりながらも、その幸福幻想が押し付ける輝かしい未来になじめなかったわたしでしたが、国家の暴力にあらがう同年代の若者たちともまた、共にたたかうことができませんでした。
それはひとえにわたしがどもりの対人恐怖症で、多くのひとの前で声を出すことが困難であること以上に、わたしが保守的で臆病で、「世の中を変える」と息巻いてみても結局は国家や社会の体制に異議申し立てをすることが怖かったからにすぎません。
高校卒業後に就職した小さな建築事務所を半年でやめたわたしはビルの清掃で生活費を稼ぎ、透明人間のように他者や世の中に見つからないようにひっそりと暮らし、ただただ年老いることを願っていました。国家が期待する若者像とも国家に抗う若者像ともかけ離れ、覇気というものがまったく感じられない不健康な若者だったわたしは、いつ暴発するかわからない危険な若者でもあったのかも知れません。
そんなわたしにも、東大安田講堂に機動隊が突入し、バリケードが解除され、立てこもっていた600人の学生が逮捕されたこと。連続射殺犯・永山則夫が逮捕されたこと。南ベトナム共和国臨時革命政府が樹立されたこと。大菩薩峠で赤軍派53人が逮捕されたこと。佐藤訪米と、それを阻止しようと武装闘争に出た新左翼各派と機動隊が激突、2500人を越える逮捕者が出たことなど、国内外の大きな出来事が押し寄せてきて、そのたびにわたしは白昼の路上で裸にされた自分の存在を知られる脅迫観に襲われました。どこにも逃げ場などない事もまた、初めからわかっていることでした。
悶々とした日々の中で、当時のわたしはピンク映画にのめりこんでいきました。というほどたくさん観たのか今は覚えていませんが、けばけばしいポスターに劣情を掻き立てられ、知り合いなどいるはずもないのに誰かに見つからないよう、とにかく早く切符売り場を通り過ぎ、小便のにおいが鼻をつく廊下を通りぬけ、素早く会場の暗闇に溶け込むように座席に座ったものでした。
観始めたころはまだ大蔵映画などのパートカラーはあるものの、白黒映画が中心だったように思います。その当時にすでに若松孝二の映画として観ていたひともたくさんいたでしょうが、わたしの場合はまだその認識はなく、自分の欲望を駆り立てる映画なら何でもよかったのですが、何本か見続ける中に、単に性的な欲望を満足させてくれるものではない、どちらかというとこんな映画がなぜピンク映画館でやってるのか疑問に思う映画が混じっていて、そのうちにクレジットで若松孝二と足立正夫という名前を覚えるようになりました。
今回の映画で、若松プロをやめるオバケ(若松プロのレジェンドのひとり・秋山道男)とめぐみとの会話で…、
オバケ「『ゆけゆけ二度目の処女』ってさ、傑作だよね」
めぐみ「うん」
オバケ「もうあんな映画作れないかも知れない。でも、ピンク映画館はガラガラ」
めぐみ「でも蠍座じゃ長い間若松孝二特集やってて、男子学生だけじゃなくて若い女の子もいっぱい来てる」
オバケ「が、エロ目当てのオジサンたちには届かない」
めぐみ「それは仕方がないんじゃないのかな」
オバケ「イケてる映画ってさ、生身の人間とか政治とか世界に興味のない、エロしか興味のない人たちが観たって、
心が動いてしまうものなんじゃないのかな?」
この頃のピンク映画は製作費300万円、撮影3日で量産でき、性的描写を入れればあとは何でもできるということで、若松孝二たちはその中で野心的な映画を作りつづけたのですが、エロだけの映画でお金をつくりだすことと、若松プロに集まる若い映画人たちが自分らしい映画をつくることとの間の切ないせめぎあいが、映画を作り続けるエネルギーになっていったのでしょう。
わたしといえば、まさしく彼女彼たちがいう「エロ目当ての20歳前後のオジサン」だったのですが、大きく心を動かされました。1965年の「壁の中の秘め事」で若松孝二という無頼の映画人の存在を知ってもなお、ピンク映画館に若松孝二の映画を観に行くのではなく、エロ映画にしてはおかしな映画だと思ったら若松孝二の映画だったのでした。
わたしがなぜ若松孝二と若松プロの映画にひかれていったのか、思い返してみると映画の登場人物たちが自分そのものだったからなのです。ピンク映画全体にセックスによる愛の表現とは程遠く、若松孝二の映画もまた女を一歩的に傷つける男たちというピンク映画のセオリーを守りながらも、傷つける男たちもまた孤独で「何者にもなれない」絶望の中にいて、その絶望からまた女を傷つけるという物語や、反対に女たちによる過激な反撃が男たちとその後ろにある国家へと向かったりします。
国家と対置し、権力や体制に対する怒りを次々と映画に込めたピンク映画時代の若松プロは、「映画の中でなら何でもできる」と、ゲバ棒や火炎瓶や銃の代わりに映画を武器に70年安保闘争をたたかった若者の集団でした。
「止められるか、俺たちを」は今の時代にドキュメンタリーでもなくフィクションでない「ほんとうの映画」として、映画でなければならなかった映画として、その切羽詰まった情熱とそれがゆえに哀しい真実を掘り起こし定着させたのでした。
「政治的な革命というのは部分的な革命に過ぎない」、「演劇集団・天井桟敷の主目的は、政治を通さない日常の現実原則の革命である」と言ったのは寺山修司ですが、若松孝二もまた映画で革命を夢見たひとで、この映画は1969年から71年までの若松プロのやけどしそうなヒリヒリとした疾走が長い時の地下道をくぐりぬけて今、街の路石を一斉に吹き上げさせ、映画が終わった後のスクリーンからあふれ出てわたしをとらえて離さない、とても危険な(素晴らしい)映画でした。