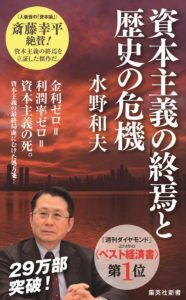恋する経済 豊能障害者労働センターの場合
豊能障害者労働センターは1982年4月に静かな出発をしました。その前年に、わたしは当初のスタッフのひとりと出会ったのですが、当時は機械メーカーで働いていたわたしには、彼の話は荒唐無稽で、とても現実の話とは思えませんでした。
「粉せっけんを売ってお金をつくり、障害のあるひともないひとも暮らしていけるようにしたい。1000袋売るとなんとかなりますから」。合成洗剤の毒性が騒がれ、環境問題への関心が高まり始めたとはいえ、3キロで900円の粉せっけんがそんな売れるとは到底思えませんでした。
そんなわたしをふくむまわりの人々の心配をよそに、彼らは築30年の古い民家を借り、車や事務机をそろえ、脳性まひの障害者2人をふくむ5人のスタッフで活動を始めたのでした。5人とも粉石けんで真っ白になりながら袋詰めをし、応援してくれる数少ない団体や個人のお宅に配達していました。案の定、粉石けんがそんなに売れるはずもなく、5人の暮らしが成り立つだけのお金には程遠く、毎週日曜日に大阪に繰り出し、募金活動でいただいたお金で食うや食わずの毎日をしのいでいました。
その頃も実は今も、豊能障害者労働センターの活動に対して、国からも大阪府からも福祉助成金はありません。障害者が働いて給料を得るためには理解のある企業や商店に雇われなければなりません。国は障害者を雇用する企業に助成金を出したり雇用環境を整備したりはしています。しかしながら、現在でも豊能障害者労働センターで働く障害者は最初から企業が雇わない障害者がほとんどで、そういう障害者の方が圧倒的に数多いのです。
ですから、これだけ福祉福祉といわれ、その負担が大きいと問題にされる現在でも、企業が雇わない障害者は働いて得る所得はなく、一人で生計を立てるだけの年金もないので親元で生活するか、生活保護をとって生計を立てるしかないのが現実です。
そこで豊能障害者労働センターは「会社が雇ってくれないのなら、自分たちで働く場をつくろう」と考えたのでした。そうなるとまた、その事業性や実態は別にして「企業」とみなされ、いくら企業への就労が拒まれる障害者の所得補償を叫んでも、「福祉」のエリアからは排除され、もともと障害者を雇用するために事業しているわけではない一般企業ともちがい、設立から10年は公的な助成制度にはまらないまま、お店を展開し、後に通信販売事業へと発展していったカレンダーの販売などをしながら、その日その日を暮らしていたのでした。
わたしは1982年の設立時から豊能障害者労働センターの運営にかかわり、5年後の1987年に会社勤めをやめ、専従スタッフになりました。
わたしは豊能障害者労働センターとの出会い、わたしもその歯車のひとつだった高度経済成長から障害者が排除されてきたことを身をもって学びました。教育の場からも働く場からも排除されてきた障害者は富の再分配としての「福祉」の対象とされることで経済成長の最終電車に間にあった人もいたでしょうが、乗り遅れたままホームに立ち尽くす人たちも数多くいたのだと思います。
ほとんどの障害者は親元にいるしかいのちをつなぐすべがなかった時代に、そのいのちをけずってでもあたりまえの市民として暮らしていこうとするひとたちとともに、豊能障害者労働センターは細々ではありますが活動をつづけてきました。
その活動の日々は年々増え続ける障害者の生活と働く場を切り開くために、お金をつくりだす日々でもありました。そんな毎日を過ごしている間に、いつのまにかわたしたちは自分が活動している小さな地域での事業から得るお金がどこから生まれ、どのような道を通り抜けてわたしたちの手の上に乗り、そのなけなしのお金が障害者の生活をかろうじて支えることでまたどこかに行ってしまう、そのプロセスに関心を持つようになりました。
豊能障害者労働センターの設立の少し前、サッチャーやレーガンによる新自由主義の嵐が世界を吹き荒れました。日本では高度経済成長が終焉し、小泉政権になって20年遅れで実行されたその政策は簡単にいうとよくないのでしょうが、福祉が経済を圧迫する「大きな政府」から、福祉や社会保障を縮小する「小さな政府」への転換でした。
実はわたしたちもまた、今までの福祉の充実は「富の再分配」でしかなく、ほんとうは再分配の対象とされるひとが「富の生産」の現場に参加していくことを求めてきました。
「富の再分配」としての福祉に疑問を持つわたしたちの活動は新自由主義を主張するひとたちと一見変らないように見えましたが、さまざまな事業をすすめてきた経験から、GDPに代表されるいままでの尺度で見ればマイナス成長でしかなくても、実は豊かで安心できる経済のシステムがあるのではないかと思うようになりました。
障害者の問題でいえば、わたしは当時も今も「大きな政府」は福祉を充実させ、「小さな政府」が福祉を切り捨てるという議論にどうしてもなじめない気持ちがあります。わたしはそれよりも、そのどちらの主張においても福祉施策の対象となる障害者を「福祉予算を消費するひと」としかとらえていないことに失望します。
どちらの場合も障害者を働く場から排除していることには変わりがなく、富の再分配の量やあり方で対立しているにすぎず、その前提として経済成長が不可欠であるとしている点でも変りがないと思うのです。
わたしはこのブログで以前、稲葉振一郎と立岩真也の対談本について書いた時に、「機会の平等」と「結果の平等」に加えて「参加の平等」を訴えましたが、本当は平等という言葉は適切ではなく、本来の働く場や暮しの場、それをつつむ社会に障害者も参加したいと思っているだけではなく、障害者の参加がこの社会の未来にとっても必要であると思っています。
それはこの社会や職場の構成員にさまざまなひとが参加し、知恵を出しあい、助け合うことが必要であるだけでなく、高度経済成長期にあたりまえとされてきた高利潤の産業、輸出を中心に付加価値が高く生産性の高い産業を育て、そうでない産業は滅びるにまかせ、助成金や補助金でまかなうやり方ではだめだと思ってきたからです。グローバル化で生産性を求める企業は海外に出て行き、その富はもう国内には帰ってきません。
それならば、国内にいるわたしたちは取り残されるのではなく、グローバリズムの悪夢からめざめ、成長神話から解放されて顔の見えるコミニュティが生みだす手ざわりのある市場をつくりだせないものかと考えたのです。この市場では生産者と消費者ははっきりと分かれてはいず、食べ物の地産地消はもとより、たとえば障害のあるひともないひとも共に働き共に給料を分け合って暮らしていけるコミュニティがあれば、そんなにたくさんのお金を必要としないかも知れないのです。
つまり、社会保障の対象となるひとの所得や働く場が確保できれば、経済成長による分配すべき富は減ったとしても、富の再分配としての社会保障費もまた少なくていいのかもしれないのです。数字だけ見ていると縮小していくようで活気のない社会のように見えますが、実はより多くのひとたち、障害者もふくめたさまざまな特徴、個性を持った人たちが社会に参加でき、ひととひととが助け合える活気にあふれた社会のように思うのです。
そんなことを考えると、水野和夫氏の唱える「資本主義が終わった後の社会」とはそんなに突飛な発想ではまったくなくて、わたしたち人間の歴史が何度も経験した「助け合い」を基盤にした、「小さな社会」の豊かさを取り戻すことなのかも知れません。