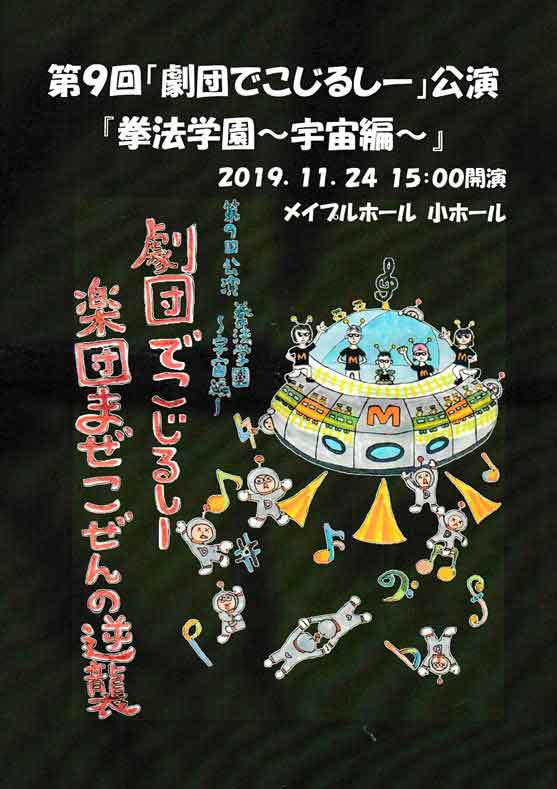「武力では解決しない。農業復活こそがアフガン復興の礎」 中村哲さん追悼1
中村哲さんが銃弾に倒れ、亡くなられました。
彼に銃を向けたひととその周辺の人たちに声を限りに言いたい。
あなた方はもっとも向けてはならない人に銃をむけたのだと…。
中村哲さんとぺシャワール会の活動を知ったのはそんなに前からではなく、2001年のアメリカでの同時多発テロと、その後のアメリカをはじめとする有志連合国軍のアフガニスタンへの爆弾投下などの攻撃が始まった頃でした。
わたしはその頃箕面の豊能障害者労働センターに在職していて、ただひたすら一日一日を暮らしていくことに悪戦苦闘していて、世界各地の紛争で無数の人々が生活の基盤を奪われ、傷つけられ、命までも奪われる過酷な現実をほんとうに自分のこととして受け止める余裕がありませんでした。
わたしはテロについては断固許せないとする一方、アメリカの「正義」をふりかざした空爆などの軍事攻撃によって、アフガニスタンの人々の命が奪われることにもまた断じて許せないと思いました。そしてなによりもわたし自身、このことがあるまでアフガニスタンの大かんばつや難民のことを知らなかった、知ろうとしてこなかったことにも申し訳なく、自分に対して腹立たしく思ったのでした。
その時、中村哲さんの活動を知りました。中村哲さんは1984年から現地に入り、最初は医療活動を展開してきたものの、「病気を治す前に命を救わなければ」と、かつては豊かな作物でほぼ100%の食糧自給率だった瓦礫を農地へとよみがえらせる活動をはじめました。
井戸掘りから始まり、渇水と洪水を繰り返す大地に川からの用水路を建設し、その建設に毎日600人々を雇用し、用水路を完成させました。建設に携わった人々だけでなく、戦争の傭兵になることでしか生活が成り立たなかったひとびとが本来の農民となって帰ってきました。
やがて植えつけた野菜が収穫され、自給自足はもちろん、市場への出荷も始まったと聞きます。
わたしたちは中村さんの地道な活動こそが、集団的自衛権や国際貢献の名のもとでの自衛隊の派遣による軍事力で押さえつける平和より、はるかに有効な平和活動だと思いました。
そして、貧者の一灯でしかないわずかな支援金をペシャワール会に送金した他、機関紙「積木」紙上でペシャワール会の活動とわたしたちの思いを綴り、募金のよびかけをしました。
下記の文章は、その時の豊能障害者労働センターの機関紙に寄せた記事です。
2001年11月 豊能障害者労働センター機関紙「積木」NO.140号より
アフガニスタンのこどもたち ぼくはあなたたちの顔を知らない
細谷常彦
9月11日の夜、ぼくはいつものように市民酒場「えんだいや」にいた。音のないテレビのブラウン管に、細長いビルの側面からあふれる煙が見えた。大変な事故が起こったと思った。それから1時間ぐらいして、それがテロであることを知った。
ぼくはアフガニスタンのことをほとんど知らない。阪神淡路大震災の時にテレビにうつった風景と、被災地の立った時の風景がまったくちがったように、テレビにうつるアフガニスタンのひとびとのくらしを垣間見ただけでは、ほんとうのすがたはわかるはずがないのだ。アフガニスタンのこどもたちのひとみと、それを酒場で見ているぼくのひとみとの間には、とてもない距離が横たわっている。
ぼくたちはこの日本で、この箕面の街で「しあわせになる」ために活動をつづけてきた。障害者がほんとうに一人の市民として暮らしていくことは難しい。しかしながら、19年前にくらべればたしかにほんの少し「豊か」になっているのだと思う。
ぼくたちのほんの少しの「豊かさ」はぼくたちが「がんばってきたからかも知れない。けれども、その一方で日本の経済システムの中にいるぼくたちのほんの少しの「豊かさ」が、アフガニスタンのこどもたちの飢えをつくったのではないと言い切れるのだろうか。あのこどもたちのかなしみと恨みにあふれたひとみが、ぼくたちには向けられていないと言えるのだろうか。それが、ぼくの感じたとてつもない距離だった。
それを承知で、ぼくたちはアフガニスタン難民支援金を送ることを決めた。ぼくたちはついこの間運営に行き詰まり、「積木」読者の方々に応援金をお願いしたばかりだ。いまも決して楽ではない。読者の方々から「そんなに余裕があるの?」と、お叱りを受けることを承知している。けれども、お許しいただきたい。どの大地の上でもどの空の下にいても、すべてのこどもたちがわくわくするはずの明日を恐れないですむように、ぼくたちはささやかな行動を起こしたいと切実に思った。
それはそのまま、日本の村や町で、この箕面の地でだれもが自分らしく生きていくことを夢みるぼくたちの活動そのものだから…。そして、アフガニスタンのこどもたちへ、ただ、生きていてほしい。その思いをお金にかえることしかできないくやしさをかみしめ…。
阪神大震災の時、わたしたちの救援活動は「助ける」ことではなく、被災障害者自身が町を復興、再生していくことにつながろうとした活動でした。
あの時、全国の「積木」読者の方々がわたしたちの行動を支援してくださいました。神戸の読者の方の家で、壊れかけている家に救援バザーの用品を取りにうかがったこともありました。
遠い空の下で、いのちが危険にさらされているアフガニスタンのこどもたちとわたしたちが簡単につながれるとは思いません。わたしたちはわたしたちの地をはなれることはできません。でもわたしたちは祈っています。ただ、生きていてほしい。
その思いをお金にかえることしかできない悔しさと一緒に、アフガニスタンで活動されているNGO「ペシャワール会」に支援金を送りました。