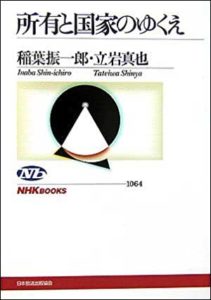稲葉振一郎・立岩真也「所有と国家のゆくえ」3
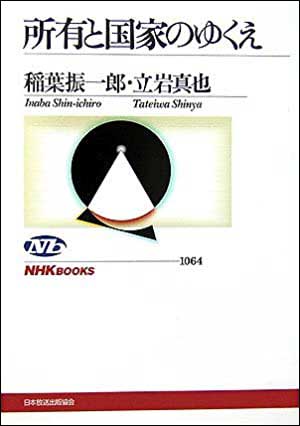
その後、豊能障害者労働センターは地域のお店を次々と開き、閉めてしまった店もありますが、現在リサイクルショップを5つ、食堂、福祉ショップと7つのお店を運営し、地域での移動販売、年に2度の大バザー、同じく年に2度の古本市、プロの古書店のご協力で毎年出店させてもらっている「天神さんの古本市」と、お店やイベントを通して地域の人たちとの交流を深めながら事業をすすめてきました。
当初は障害者がお店をすることに地域のひとびとにも障害者本人にも、そしてまわりのわたしたちにもそれぞれの違和感があり、ぎこちない部分もありましたが、いまではすべてのお店を障害者がにない、地域のひとびとも普通にお客さんとしてお店に来てくれるだけでなく、「何かあった時には助けてくれる」という気持ちをもっていただくセーフティネットの拠点にまで成長しています。
ここで、また稲葉さんと立岩さんの本に戻りますが、「労働」、「機会の平等と結果の平等」について議論されていて、その中で結果の平等だけではなく、労働の分配、ワークシェアリングという言い方で労働の場への障害者の参加の可能性についても考察されています。
たしかに、機会の平等では企業が求める「労働能力」や「生産性」というところで障害者が排除されてしまう現実があります。ですから労働能力のあるひと、生産性の高いひとが働き、富を生み出して、その富を排除したひとたちに分配する方が手っ取り早く社会保障が充実すると考えるひとも、機会の平等を保障するのだからその分配を制限しようとするひとも、障害者とともに働くことはもとから念頭にはありません。
二人の論議ではそこをもう少し踏み込み、労働協同組合にみられるようなアソシエーション(友愛)による労働の分配などに言及されています。ただ、二人とも協同組合には懐疑的で、それは社会主義国家で市場原理を一部導入する形での実験が行われて失敗した事例や、所得の分配と結果の平等をすべてのひとが納得しないのですから、友愛などを提唱しても国家や組織の押し付けでしかないということでしょう。
このあたりを読んでいて、私事ですが、わたしが豊能障害者労働センターの専従スタッフになった時、あるひとが言った言葉を思いだします。彼はこう言いました。「あなたが専従スタッフになることと、会社を辞めずに支援金を出し続けるのと、どちらが労働センターにとってうれしいのかな」と。
たしかに、わたしは会社勤めをしていた時はそれなりの収入があり、そのころも資金援助をしていましたが、その金額を増やす方が労働センターのスタッフになるよりも喜ばれたかも知れません。
けれども、わたしは豊能障害者労働センターの専従スタッフになりたかったのでした。わたしが勤めていた会社は 私の妻の父親がオーナーで、わたし自身の将来もある程度は約束されていました。けれども、そのことがわたしにはとても苦しいことでした。会社自体は景気もよくて、他の会社よりも給料もとてもよかったし、会社の雰囲気も一般の会社よりずっと家庭的で、福利厚生も行き届いていた方だと思います。社員間の給料の差もそんなに大きい方ではなかったし、会社ではそれなりのモチベーションを持って働いていました。それでも、一般の会社にはちがいがなく、社員さんとの間も、また経営者としての妻の父親との間も、豊能障害者労働センターのひとたちのようには絆をつくることはむずかしかったのでした。
どこに違いがあるのかというと、豊能障害者労働センターはそのころはなおさら貧乏で、事業収益などほとんどなく、もちろんそのころは福祉助成金もまったくない状態でしたが、それでも入ってきた少ないお金をみんなで分け合っていたのでした。それはいまも基本的には変わっていません。
脳性まひの青年がもう一人入ってきて、3人の脳性まひの青年の昼間の介護とひとりの夜の介護を男性スタッフと少ないボランティアで支え(わたしもそのボランティアのうちのひとりでした)、実際仕事どころではなかったのですが、それでも豊能障害者労働センターのひとたちには大きな夢がありました。
障害のあるひともないひともともに働き、ともにお金を分け合いながら、彼らが見た夢は障害者があたりまえの市民として暮らせる街をつくることでした。それは今では共生社会とか、あるいは自立生活運動とか言いますが、彼らにはまだそんな言葉は届いていませんでした。
届いてはいませんでしたが、彼らが見た巨大な夢はとてもステキな夢でした。そんなことが実現するはずはないとまわりの人たちは言い、彼らとかかわりを持つことを止め、去って行きました。それでもかれらはその夢が絶対にまちがっていないと信じて、あきらめませんでした。
わたしもまた、その夢を一緒に見たいと思いました。そのために、いま持っている多くのものを捨てることになっても、その夢に私の人生を賭けてみたいと思ったのでした。
豊能障害者労働センターの活動は、現在は協同労働組合やソーシャルビジネス、社会的企業、コミュニティビジネスなど、立岩さんや稲葉さんの言う「アソシエーショニズム」にあたると思います。
たしかに、わたしたちの活動はこの社会の大勢から言えばマイノリティーの活動で、一部の人の間でしか通用しない活動と言えるのかもしれません。しかしながら、たとえばアメリカの音楽シーンを見れば、1930年代から現在にいたるまで、マイノリティーといわれるひとたちの間から新しい音楽が生まれ、その音楽が世界を席巻するメジャーになっているではありませんか。
わたしたちの活動もまた、いつかは日本社会の、いや世界のたくさんのひとびとに届くメジャーな活動にならないとは言い切れないと、わたしは思うのです。
二人の議論にもどせば、機会の平等も結果の平等も必要で、そのためには稲葉さんが言うように経済成長も必要であるのかもしれませんが、たとえば障害者がいままで参加しなかった労働の場に参加するだけではなく、豊能障害者労働センターのように経営にも参画することで、新しい労働の場の創出から生まれる新しい商品、サービスの創出もあり得ないことはないのではと思うのです。