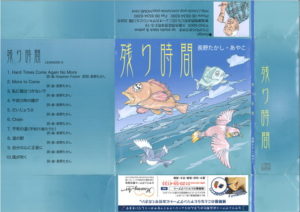一本の映画の片隅に取り残された小さな物語を歌い続けてきた友部正人の旅

12月5日、能勢の「Cafe気遊」で友部正人のライブがありました。
2、3か月前から友部さんが気遊さんに来ることを知っていて予約していたのですが、実は日にちを6日とまちがえていて、家で夕飯を食べていた時に気遊のマスター・井上さんから連絡があり、「今始まったところです」と聞き、車に乗れないわたしは急遽近所に住む妻の弟に乗せてもらい、気遊さんへ急ぎました。
すでに一部の終わりかけでしたが、なんとか「特別な夜」を逃がさずにすみました。
そんなわけで、気遊さんに到着した時は前作アルバムに収められた「マオイの女」の演奏の途中でしたが、井上さんの計らいで会場に入ることができました。それもなんと一番前の席が空いていて、今まで何度もライブに行きましたがこんなに近くで友部さんが歌う姿を見たのは初めてで、どきどきしてしまいました。
一部の始まりがどんな様子だったのか知る由もありませんが、途中から聴いていると路上のどこからか聴こえてきた歌に引き込まれて、思わず立ち尽くしてしまったような感覚でした。そして、友部さんの若い時からずっと変わらない弾き語りのスタイルと、そのだみ声で舌っ足らずの歌声は年を重ねたわたしの心に瑞々しい感覚をよみがえらせるのでした。友部正人という一人の歌うたいが少年のような柔らかい心と孤独な夜を持ち続け、半世紀を越えても歌いつづけている…、そのいとおしさが胸に迫ってきました。
1970年、ビートルズが解散しました。
わたしの1960年代は、いわば逃げつづける10年でした。社会性のかけらもなく、どこにも隠れ家がないのにそれでも隠れ家を探し続ける貧乏でどもりで私生児の少年だったわたしには、いままでもこれからもこの町もよその町も、いいことなどなにひとつないと思っていました。
世の中すべてから脱出したかった。自分という存在を消しごむで消してしまいたかった。
高校を卒業してからヒッピーまがいの暮らしを経て1970年代にいたる安保闘争とベトナム戦争反対といった激動の時代、同世代の若者たちが社会や政治に異議申し立てをすることに賛同しながらも、実際の行動には参加しなかったわたしにとって、皮肉にも激動の時代の終焉はよど号事件ではなく、ビートルズの解散でした。
同時代を生きた「政治的人間」がその後の生きづらい高度成長の始まりに戸惑ったであろうまさにその時、同じ青い時をまともな仕事もせずにヒッピーまがいの暮らしをしていたわたしもまた、時代の喪失感とあんなに騒がしく猥雑な街が静かになっていくことに無性にいらいらしていました。
わたしはフォークソングが苦手だったのですが、三上寛の追っかけをするようになり、その時に友部さんもよく出演していて、三上寛とはスタイルがちがうもののその歌は心に深く突き刺さり、そのやさしい痛みがいつまでも心に残ったのでした。
日本のフォークソングは1965年ぐらいから一大ブームになっていましたが、わたしにとっては藤圭子の「夢は夜ひらく」とともにやってきた三上寛の「ひびけ!電気釜」と、友部正人の「大阪へやって来た」が最初の出会いでした。メッセージソングやプロテストソングでもなく、また最近のJポップへとつながる個人の感情をストレートに歌う歌でもなく、日常の心象風景の背後にひそむ時代の闇を淡々と歌い、火傷しそうな青春という刃で時代の風と立ち向かい、極限にまで純化された孤独な心を圧倒的な言葉で歌う友部さんの歌は、70年以後の人生を生き続けなければならなかったわたしの伴走歌でした。
間近で歌う友部さんはあの時とまったく変わりませんでした。およそパフォーマンスとかエンターテインメントとは無縁で、それでいてわたしの心のもっとも柔らかいところに静かにしみこんでいく歌たちは、いったいどこで生まれてこの場にたどり着いたのでしょうか。ひさしぶりにライブを聴いて、このひとのかたくななまでにすがすがしい歌がわたしの澱んでいた心の水を波立たせ、あの「やさしい痛み」がよみがえりました。
おそらくこれから何年も、さまざまな分野の表現がコロナを抜きには成り立たないと思うのですが、その中でも友部さんがこの状況をどのように昇華し歌うのかを想像することはとても刺激的なことでした。実際、彼の半世紀を超える長い旅のどの一日も、歌うことを抜きにしてはあり得なかったと想像できます。ほんとうに不思議なことですが、彼の歌はどの歌にも伝えたいメッセージなど一つもないと思えるのに、日常生活から生まれる具体的な言葉たちはすでに時代を証言するリアルな歌になっていて、どんなメッセージソングよりも時代を表現していることにいつも驚かされます。
この日のライブの間、いつにもまして死が隣り合わせになった時代に生き続けなければならないわたしたちの究極の孤独にどんな行き先があるのかを、今読み返している村上春樹の「海辺のカフカ」の孤独な15歳の少年の旅を思い返しながらずっと考えていました。村上春樹が大衆的で三文小説風に時代の切り口からにじみ出る血の色をたどり、いくつもの「物語」を生み出すように、友部さんもまた、ますます過酷になる時代を生き抜くための「物語」…、一本の映画の片隅に取り残された小さな物語を歌い続けてきたのだと思います。友部さんの長い旅の後から追いかけてくる彼の歌は、それがゆえに時代の記憶を持ち続けることでしょう。
4年ぶりのアルバム「あの橋を渡る」発売を記念して気遊さんに現れた友部さんのライブはあっという間に終わりました。新作アルバムは東北の盛岡、吉祥寺、仙台、南三陸と駆け回り、その場所の空気を呼吸しながらレコーディングされたそうで、一曲目の「あの声を聞いて振り返る」は、震災10年に近づく今だからこそ胸に迫る歌でした。
そして、間に合って聴くことができた究極のラブソング「バレンタインデイ」と、アルバム最後の曲で目を背けても背けても迫ってくる理不尽な現実を淡々と歌う「空の鰯」は、コロナの時代だからこそ生まれた歌だと思いました。
最後になりましたが、わたしの思い違いに気づいてくださり、わざわざご連絡いただいた気遊のマスター・井上さんに感謝します。
友部正人ニューアルバム「あの橋を渡る」amazon
本文にも書きましたが、「バレンタインデー」は長い時間を通り抜けてきたわたしには胸が迫るものがあり、涙が出ます。このアルバムに収録されているどの歌もいま生まれたばかりで、これから人々の心を一つずつ慈しみながゆっくりと通り過ぎる旅の始まりのようです。